日本は世界でもトップクラスの地震大国。いつどこで被災してもおかしくはありません。
したがって、住まいを選ぶ際には「いざという時に、自分と家族をしっかり守れるか」という防災面を重要視する人も多いでしょう。また地震が発生した時に備えて、備蓄や対応の準備といった防災に力を入れている人も多いと思います。
この記事では、マンションにお住まいの方、またこれからマンションで暮らそうと考えている方に向けて、マンション特有の地震対策についてまとめました。ぜひ防災の参考にしてください。
毎月ポイントが貯まる
お得な「アルファあなぶきStyle会員サービス」
「アルファあなぶきStyle会員サービス」の無料会員になると、
そんな住まい情報と一緒に毎月1万ポイントをお届け。
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもさらにポイントが加算されます。
貯まったポイントは、「毎月のプレゼント応募」や「将来の住まい購入時の割引(最大50万円)」に使えます。
マンションで地震が発生したら。その時とるべき対応
地震が発生した時、もっとも重要なのは人命です。まずはご自身の安全確保を最優先し、落ち着いて対応しましょう。
身の安全を確保する

なによりも優先されるのが、安全の確保です。なにをおいても最優先で行動しましょう。
- 火の元から離れる
- 落下物・倒壊物から頭や体を守る
- 台所や本棚など、落下物や倒壊物のある場所から遠ざかる
- 机の下(物が落ちてこない・倒れてこない・押し寄せてこない場所)へ隠れる
揺れが強かったり長く続くときは、思うように身動きが取れないこともあります。可能な限り上記の順で行動してください。
住居内では、火の元がないこと、落下物が少ないことから、トイレや浴室が比較的安全な場所だと言われています。
火の始末をする

揺れがおさまったら、真っ先に行うことは火の元の確認です。
火災という二次災害を防ぎましょう。
一般的にガスは、大きな地震が起こるとガスメーターの安全装置が作動し、自動で火が消えることがほとんどです。しかし、念のために確実に消火できているか確認した方がいいでしょう。あわせてガス漏れが起きていないか(ガスの臭いがしないか)も合わせて確認を。
さらに電気ストーブなどの家電も、消えているかを確認しておきます。
玄関扉が開くか確認しよう(避難経路の確保)

気持ちが落ち着いたら、玄関ドアが開くかどうか確認しましょう。
最近では「耐震ドア」という変形しづらい玄関扉が採用されることも増えましたが、揺れの影響で玄関扉が変形し出られなくなるケースはあります。
避難所に行かずに自宅に留まる場合でも、出口が確保されているかの確認は重要です
扉が開かない場合は、別の避難経路の確保を考える

玄関扉が開かない場合は、別の避難経路を考えましょう。
マンションの場合は、バルコニーです。
バルコニーの戸境の隔て板は、突き破ることができるようになっています。バルコニー経由で別の住戸に入り、そこの玄関扉から避難しましょう。
バルコニーの避難ハッチから避難が必要な場合は、早めに避難することをおすすめします。
ご自身のお部屋のバルコニーに避難ハッチがなくても、同じ階のどこかの部屋のバルコニーに避難ハッチがあります。落ち着いて戸境の隔て板を突き破り、避難ハッチに向かいましょう。

マンション自体が孤立していないかの確認も
地震による土砂崩れなどで、マンション自体が周辺から孤立していないかなどの確認もしておきましょう。
孤立の例
- 道が土砂崩れや崩壊などでふさがれている(ふさがれる可能性がある)
- 川の氾濫や津波などで孤立する可能性がある
- 電話などが不通になり、外部との連絡手段がなくなる
トイレの水は流さない


大きな地震が起きた後は、トイレの水は流さないようにしましょう。揺れによって排水管が壊れた場合、水を流してしまうことで、下の階で下水が漏れてしまうケースがあります。
非常用の携帯トイレの備蓄がおすすめです。備蓄の目安は、1日5枚程度を3日分~7日分です。
避難するときにエレベーターを使わない


基本的なことですが、避難するときにエレベーターを使ってはいけません。階段を使って避難しましょう。
大きな地震の際には、エレベーターは自動停止し、しばらく動きません。また意図しないタイミングで停電が発生し、閉じ込められることも考えられます。
マンション内に階段が複数ある場合は、どの階段を使うべきなのかを事前に確認しておきましょう。
基本は在宅避難がおすすめ


2011年の東日本大震災以降、可能であれば在宅避難を呼びかける自治体が増えています。
そもそも避難所は、自宅を失った人や危険が及ぶエリアにいる人など、立ち退き避難が必要な人のためのものです。受け入れ可能な人数に制限もあることから、マンションでは基本的には在宅避難を考えましょう。新耐震基準のマンションなら震度6程度でも倒壊しない耐震性があるので、敢えて不慣れな環境下に避難しに行くよりもストレスなく避難生活ができるはずです。
自治体からの情報や支援物資など、在宅避難者でも受取り可能(マンションの場合は、代表者が定期的に避難所に取りに行くことになります)になっている自治体も多いので、安心してください。
ただし、津波や土砂災害などマンションに危険が及ぶ場合はもちろん、年齢や体調に不安がある場合や、高層階での揺れが怖い場合などは、避難所に行くことも選択肢に入れましょう。
マンションで地震に備えておくべきこと
地震に限らず災害はある日突然発生するものです。万が一を想定したマンション住まいにおける地震への備えについて解説します。
防災グッズの準備・在宅避難のための備蓄をしておく


マンション自体は無事で在宅避難をしようと思っても、インフラ(電気・ガス・水道)が止まってしまうこともあります。そういったことを想定して、食品や日用品を備蓄しておきましょう。
準備物例
- トイレ用品(洋式便器にはめるビニール袋、中に固化剤入りのものが便利。1人1日5枚を1週間分)
- 非常食(煮炊きしなくても食べられるものを、最低家族の3日分用意する)
- 飲料水(可能なら1週間分…3リットル×7日×人数分)
- 食料品(米・乾麺・インスタント食品・野菜など)3日分以上
- 携帯用ガスコンロ
- 懐中電灯
- ローソク、マッチ、ライター
- 現金(100円玉、10円玉を多めに)
- 携帯電話充電用手動発電機付きラジオ
- 消火器
- 小型発電機
- 持病の薬(3日分~7日分)
- メガネ(買い替えたときに、古いメガネを非常用にするのがおススメ)
- おくすり手帳(持病の薬が分かるので、処方箋なしで薬剤師に薬をだしてもらえる場合がある)
- その他(生理用品・医薬品・介護グッズ・ペット用品など)




大きな家具が転倒してこないように固定する


大きな地震では、食器棚や本棚といった大きな家具が転倒する危険があります。特に揺れやすいと言われる上層階では、転倒の可能性がさらに高くなります。身を守るために、しっかり固定しておきましょう。
固定するための器具は、ネットショップやホームセンターで入手することができます。
家具の固定方法は消防庁などが公開しています。
あわせて、キッチンの吊り戸棚には重いものを入れない、ベッド周りに倒れてくるものを置いていないかなど、ものの配置も見直しておきましょう。
緊急連絡先を家族間で共有し、いざという時の行動を決めておく
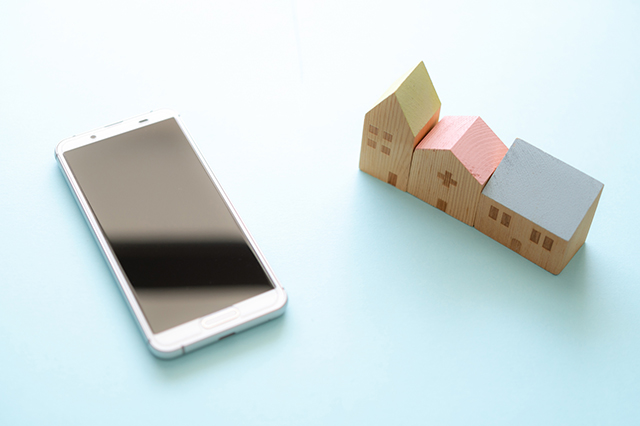
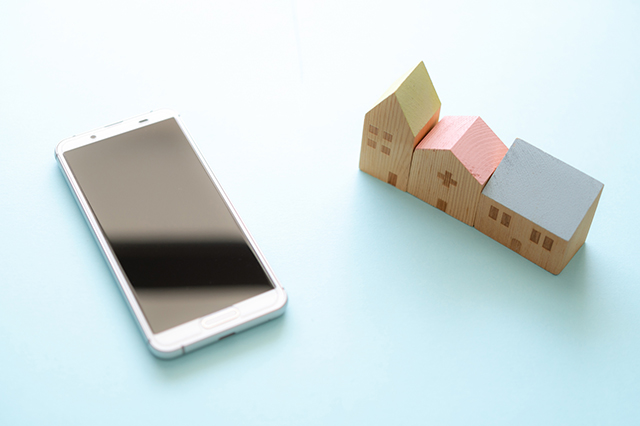
万が一の時にどこに連絡を取ればいいのかを準備し、家族間で共有しておきましょう。携帯の充電が切れた時のことも考えて、どこかにメモしておくと良いでしょう。
さらに家族とはぐれた場合に備えて、待ち合わせ場所を決めておくことをおすすめします。
災害時は「171」をダイヤルすると災害用伝言ダイヤルセンターに繋がります。毎月1日と15日は練習ができるようになっていますので、利用してみることもおススメです。
地震保険に加入する
地震保険に加入しているか、今一度確認をしておきましょう。地震保険は火災保険に付帯して加入するものですが、火災保険に入っているからといって、必ず地震保険に入っているとは限りません。
あわせて家財保険にも加入しているかを確認しましょう。
例えば地震による損壊で上階からの漏水があり家電が壊れた場合、家財保険に加入していないと全て自己負担になってしまいます。


ハザードマップを確認する


自治体が作成したハザードマップで、事前に揺れやすさや津波・洪水の被害予測程度を知っておきましょう。
ハザードマップは自治体のホームページで閲覧できるほか、窓口でもらうことができます。
特に海に近いマンションの低層階にお住まいの人は、津波発生時にマンション上層階へ避難した方が良いのか、指定の避難所に避難するべきかを確認しておきましょう。万が一の時に焦って決断せずに済みます。
避難経路・避難所の場所を確認する


マンションでは、基本的には在宅避難がおすすめです。しかし自宅での避難が難しい場合は、避難所に避難することになります。その時に備えて避難経路と避難所の場所を確認しておきましょう。
地震の揺れで玄関扉が開かなくなった場合は、バルコニーにある避難ハッチを使って脱出することになります。その時になって慌てないよう、避難ハッチの場所と使い方を確認をしておきましょう。



避難所の場所を確認する際には、実際にどのルートを通るのかをシミュレーションしておくと良いでしょう。また家族がバラバラになった時を想定して、待ち合わせ場所を決めておくことをおすすめします。
住んでいるマンションの耐震性を確認する
住んでいるマンションが安全かどうかは気になるところです。ここではお住まいのマンションの耐震性を確認するための方法について紹介します。
1981年以降の新耐震基準でできたマンションかどうか
お住まいのマンションの建築確認がおりた年月日が1981年(昭和56年)6月1日以降なら、新耐震基準のマンションであり、倒壊リスクは少ないと言えるでしょう。
1981年(昭和56年)は建築基準法の改正があり、耐震性に関わる基準が大きく見直された年です。
旧耐震基準では「中規模の地震動(震度5強程度)」で倒壊しないことが特徴でしたが、新耐震基準ではよく発生する地震での被害を軽くすることに加え、まれに発生する「大規模の地震動(震度6強~7程度)」で倒壊・崩壊するおそれがないことが追加されました。
大きな地震で建物が倒壊しても、周りの人命に被害が及ばないことに重点がおかれています。
| 旧耐震基準(1950年制定) | 新耐震基準(1981年制定) | |
|---|---|---|
| 震度5程度 | 倒壊しない | 軽度なひび割れ |
| 震度6以上 | ーーー (規定されていない) | 倒壊しない |
その基準が適応となるのが、1981年6月1日以降に建築確認がおりた建物です。お住まいのマンションの建築確認がおりた年月日を確認してみましょう。


1981年よりも前の建物でも、「適合証明を受けている」「耐震工事を行っている」などで新耐震基準を満たしている建物もあります。
免震構造かどうかを確認することは難しい
免震構造では、免震装置(アイソレータとダンパー)によって地震の揺れを建物全体に伝わりにくくし、建物の内部の揺れを軽減しています。建物自体も損傷を受けにくい構造なのですが、導入コストが高いため採用されることは非常に稀です。
お住まいのマンションが免震構造かどうかを、書類で確認することは難しいでしょう。性能評価書があれば免震構造かどうかの確認をすることができますが、無い場合は書類上で確認することはできません。
これから購入を検討している場合は、物件の営業スタッフに確認することをおすすめします。
まとめ
地震への備えというと、つい防災グッズのことばかりを考えてしまいがちです。
しかし備蓄に加えて、地震後の対応を事前にシミュレーションしておけば、焦らずに落ち着いて行動することができます。ぜひこの記事を防災・減災の一助としてください。
暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?
「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、
- 住まいに関する最新情報
- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を
あなたの興味にあわせてメールでお届けします。
会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。
貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!
お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?
その他の記事はこちらをCHECK
https://journal.anabuki-style.com/

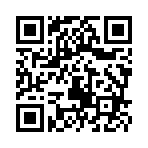
編集・発行


<著作権・免責事項等>
【本紙について】
・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。
・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。
【著作権について】
・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。
・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。
・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。
【免責事項】
・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。
・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。
・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。
・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。






