1月の和名は「睦月(むつき)」。親族一同が集まり宴を催すなどして睦み合う(むつみあう=互いに親しみ合うこと)ことから、「睦び月」と呼ぶようになったとされています。家族や親しい人たちと集まることが多いこの月にぴったりの呼び名です。
いよいよ冬本番を迎えるこの月。冷たくピンと張り詰めた空気が、新年らしさを盛り上げます。
風さえて今朝よりも又山近し(暁台)
江戸時代の俳人・加藤暁台が詠んだように、寒さが極まって冴え渡った空気は、遠くの景色を一段と鮮やかに見せてくれます。何もかもが真新しく見えるこの月。
そんな1月のくらしと風情を、歳時記とともにお届けします。
1月のこよみ
1月5日「小寒」(二十四節気)
小寒は、いわゆる「寒の入り」のこと。
この日から節分(立春の前日。2026年は2月3日)までが「寒の内」と呼ばれる期間です。

寒風が吹き、降雪が本格的になるなど、寒さがいよいよ厳しくなる頃。一年で最も寒い時期の始まりを告げる節気です。
この日からは寒中見舞いを出し始めます。寒さの中で相手の健康を気遣う、冬ならではの挨拶です。
1月17日〜2月3日「冬土用」(雑節)
雑節のひとつ「土用」は、土公神(どくじん)という土を司る神様が支配する期間のこと。
立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、期間中は土を動かす作業(土いじり、地鎮祭、井戸掘りなど)を避けるべきとされてきました。
しかし18日間もの間、ずっと作業ができないのは実生活に支障をきたします。そこで土公神が地上を離れる日を設け、その日に限っては作業をしても差し支えないとされました。これを「間日(まび)」と呼びます。
ちなみに2026年の冬土用の間日は、1月17日・19日・28日・29日・31日。
土用というと夏の「土用の丑の日」が有名ですが、実は年に4回あるのです。冬の土用は、春の訪れを待つ静かな準備期間といえるでしょう。
1月20日「大寒」(二十四節気)
大寒は、一年でもっとも寒いとされる時期。寒稽古など、寒さに耐える修練の行事が行われる頃です。
厳しい寒さは、暮らしにとっても恵みでもあります。「寒仕込み」といって、この時期の冷たく清浄な空気を利用して酒や味噌を仕込むのに最適な季節なのです。

寒の味噌仕込み
自家製の味噌を仕込むのも、まさにこの時期。寒の時期に仕込むと熟成期間が長くなるため、旨みの強い味噌に仕上がります。

大寒の頃は、ちょうど秋に収穫したばかりの米(麹)や大豆が出回る時期。新鮮な素材を使うことで、よりいっそう美味しい味噌ができあがります。厳しい寒さが、豊かな味わいを育むのです。
1月の年中行事とイベント
1月1日「元日」(国民の祝日)
元旦は、年の初めを祝う日。厳密には元日の午前中のことを指します。
「旦」は朝・夜明けという意味。新年の神様である「年神様」がその年の幸福をもたらすため、午前中に各家庭に降臨するとされていたことから、元日の午前中が特に重要視されてきました。
年神様は日の出とともにやってくるという説もあります。新年の日の出時刻は、国立天文台のサイトで確認できます。各地で異なりますが、この時期の太陽は南東やや東の方角から昇ります。

若水(わかみず)
元日の朝には水を汲む習慣があり、これを「若水」と呼びます。
若水は一年の邪気を祓うものとされており、年神様へのお供えや、家族の食事の支度、お茶を点てることなどに用いられました。新しい年の最初の水には、清らかな力が宿ると信じられてきたのです。
1月2日「書き初め」(年中行事)
書き初めは、年が明けて初めて毛筆で書をしたためる行事です。
かつてはおめでたい詩歌を書いていましたが、現代では一年の目標や抱負を書くのが一般的でしょう。新しい年への想いを、墨の香りとともに紙に刻む——凛とした気持ちで一年を始める、日本ならではの習わしです。

江戸時代以前、書き初めがまだ宮中行事だった頃には、元旦に汲んだ水「若水」で墨をすり、その年の恵方に向かって行うのが作法だったそうです。一年の始まりにふさわしい、清らかで神聖な儀式だったのですね。
1月7日「人日の節句(七草)」(節句)
人日の節句は五節句のひとつで、七種粥を食べることから「七草の節句」とも呼ばれます。
もともとは無病息災を願って食べられた七草粥ですが、おせち料理などで疲れた胃腸を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養を補うという実用的な効能もあります。

春の七草
春の七草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(蕪)、スズシロ(大根)。いずれも青菜で、ビタミンを豊富に含んでいます。
正月明けのこの時期には、七草がセットになったものがスーパーに並びます。新しい年の健康を願いながら、ぜひ食卓に取り入れてみてください。
1月11日「鏡開き」(年中行事)
鏡開きは、年神様にお供えした鏡餅をおろし、無病息災を祈って食べる行事です。
松の内を1月7日までとする地域では11日が鏡開きですが、関西など15日までを松の内とする地域では、15日に行います。地域によって日付が異なるのも、鏡開きの興味深いところです。

「開く」という言葉の由来
もとは武家社会の行事であったため、「刃物を用いて切るのは縁起が悪い」として、手や木槌を用いて割ることになりました。
同様に、鏡「開き」となったのも、「割る」「切る」などの忌み言葉を避けるためです。縁起を大切にする日本人らしい配慮が、言葉にも表れています。
1月15日 小正月・どんど焼き(年中行事)
「小正月」とは、元日を「大正月」と呼ぶのに対しての名前です。
年神様を祀る行事である大正月に対して、小正月はその年の豊作を願ったり穢れを祓うなど、農業や家庭に関する行事が中心となります。
餅花(もちばな)
小正月を代表する飾りが「餅花」です。紅白の餅を柳や梅などの枝に飾り付け、実った稲穂に見立てたもの。豊作を願う予祝の飾りとして親しまれてきました。
養蚕が盛んだった地域では、繭に見立てたことから「繭玉」と呼ぶこともあります。

どんど焼き
小正月に行われるどんど焼きは、穢れを祓うための火祭りです。
大正月に飾っていた注連飾りや古い札を持ち寄って燃やす火は神聖なものとされ、この火で焼いた餅や団子を食べれば病気をしない、灰を持ち帰って家の周りに撒けば厄を祓うと考えられています。

また、この煙に乗って大正月にやってきた年神様が天に帰っていくとも言われています。一年の始まりを締めくくる、清めの儀式なのです。
1月の自然を表す「ことば」

上旬:正月の余韻と祝いの気配
富正月│とみしょうがつ

富正月とは、お正月の三が日に降る雨や雪のこと。
おめでたい日に降る雨は、普通なら残念に思えるかもしれません。しかし昔の人々は、これを豊作の前兆と捉え、「富」をもたらす縁起の良いものと考えました。「御下がり(おさがり)」と呼ぶこともあります。
天から降る恵みに感謝する——自然とともに生きてきた日本人らしい、前向きな発想が感じられる言葉です。
初日影│はつひかげ

元日の朝、初めて差し込む日の光を「初日影」と呼びます。
一年の始まりを静かに照らす、希望を含んだ冬の光。窓辺に届くその光に、新しい年への期待と清らかな気持ちが重なります。
初日の出のドラマチックな美しさとは違う、穏やかで優しい新年の訪れです。
松の内│まつのうち

松の内とは、正月飾りをして年神様を迎える期間のこと。
門松や注連飾りが家々を彩り、おせち料理や雑煮で新年を祝う特別な日々です。華やかさの中に、まだ日常へ戻りきらない静けさがあります。
地域によって異なりますが、一般的には1月7日まで、関西などでは15日までとされています。松の内が明けると、日常が静かに戻り始めます。
中旬:冬の静けさが深まるころ
寒晴│かんばれ

空気がきりりと冷え、雲ひとつない冬晴れの日を「寒晴れ」と呼びます。
光は明るく、空は高く澄み渡っているのに、どこか凛とした緊張感があります。寒さと晴天が同居する、冬ならではの清々しい天気です。
深呼吸すると冷たい空気が肺に染み入り、遠くの景色までくっきりと見える——そんな日は、寒さの中にも気持ちの良さがあります。
月冴ゆる│つきさゆる

寒さの厳しい冬の夜、澄み切った大気の中で冴え冴えと輝く月を表す言葉です。
「冴ゆる」は、寒さが極まった様子を意味します。凛とした刺すような寒さ、凍てつくような厳しい寒さ。そんな空気が研ぎ澄まされた夜、月はいつもより鋭く、硬質な光を放ちます。
「月冴ゆる」という言葉には、寒さが極まった時の大気の透明感、引き締まった空気の感触、その中で青白く輝く月の光——冬の夜の本質が、すべて込められています。
氷柱│つらら

屋根先や木の枝から垂れ下がる氷の柱を「氷柱(つらら)」と呼びます。
日中に溶けた雪や水が、夜の冷え込みで凍りつき、少しずつ成長していく様子は、自然が作る冬の造形です。寒さが形となって現れた、冬ならではの景色。
朝日に照らされて透き通る氷柱は、儚くも美しく、冬の厳しさの中にある静かな輝きを見せてくれます。
下旬:厳冬と春待ちの気配
山茶花散らし

厳冬の頃に降る、山茶花の花を散らしてしまうような冷たい雨を「山茶花散らし」と呼びます。
山茶花の花は椿に似ていますが、椿のように花ごと落ちるのではなく、花びらが一枚一枚バラバラに散るのが特徴です。冷たい雨に打たれて、鮮やかな紅や白の花びらが地に散っていく様子は、冬の寂しさと厳しさを感じさせます。
華やかに咲いていた花が、雨とともに儚く散る——冬の情景を繊細に捉えた、美しい言葉です。
寒の水│かんのみず

一年で最も寒い時期、寒の内に汲まれる水を「寒の水」と呼びます。
この時期の水は雑菌が少なく、腐りにくいとされてきました。澄み切った冷たさは、身を清める象徴ともされ、酒や味噌などの寒仕込みにも用いられます。
冷たく、清らかで、力強い——厳しい寒さが生み出す、特別な水です。
春隣│はるとなり

まだ寒さの中にありながら、ふとした光や空気に春の気配を感じることを「春隣」と呼びます。
日差しの角度がわずかに高くなったこと、風の冷たさが少しやわらいだこと、梅のつぼみがほころび始めたこと——そんな小さな変化に、春が隣まで近づいている予感を覚える季節です。
冬はまだ終わらない。けれど、春はもうすぐそこに。そんな希望を含んだ、美しい言葉です。
今月のアンケート
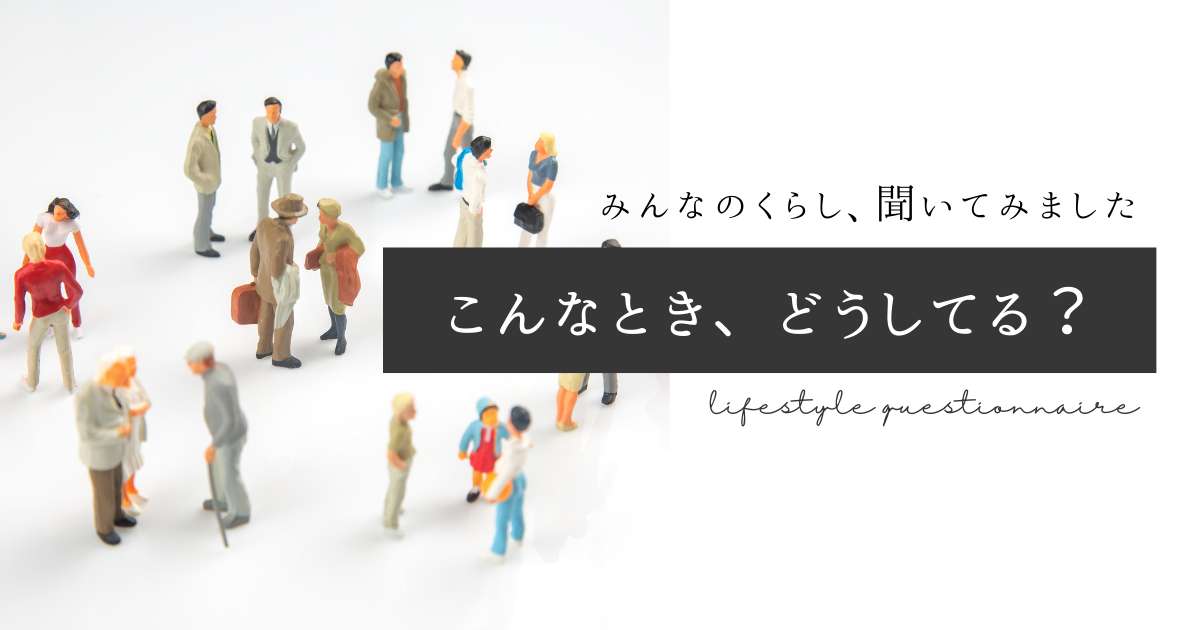
わざわざ聞くほどでもない。でも聞きにくい。そんな日常生活のちょっとした疑問——「そういえば、みんなどうしてるんだろう?」。
気になっているけど誰にも聞けなかったアレコレを、リサーチしてお届けします!
今月のお題は「手帳」

予定を書き込み、日々の出来事を記録する手帳は、暮らしを支える身近な道具のひとつです。
最近はスマホでスケジュール管理をする人も増えていますが、紙の手帳ならではの良さを感じている人も多いのではないでしょうか。書き込む楽しみ、ページをめくる手触り、一年を振り返る時間——手帳には、デジタルにはない味わいがあります。
年末年始は、今年の手帳を見返したり、来年の手帳を選んだりする特別な時期。あなたは手帳をどのように使っていますか?皆さんの手帳との付き合い方について、教えてください。
回答期限:2026年1月26日(月)
アルファあなぶきStyleのサイトに移動します
前回の「ソファ」の集計結果をみる

リビングに足を踏み入れたとき、真っ先に視界に飛び込んでくるソファ。それは単なる家具ではなく、家族が寄り添う団らんの舞台であり、ひとり静かに過ごす場所であり、暮らしの中心的存在です。
革の質感に惹かれる人もいれば、ファブリックの柔らかさを選ぶ人もいる。サイドテーブルひとつとっても、その選び方には住まい手の美学が表れています。座り心地、素材、フォルム——ソファを選ぶという行為は、実は自分らしい暮らし方を選ぶことなのかもしれません。
今回は、皆さんがどんな想いでソファを選び、どのように日々を共にしているのか伺いました。
アルファあなぶきStyleのサイトに移動します
※集計結果の公開日が変更になり「回答締切日の翌月10日頃」となりました。今月は2025年10月17日~2025年11月25日に実施した「ソファに関するアンケート」のお届けいたします。
次回の「くらしの歳時記」は2月・如月編。
寒さの中に、少しずつ春の気配が混じりはじめる頃の、澄んだ空気とやわらかな光をお届けします。
お楽しみに!
暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?
「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、
- 住まいに関する最新情報
- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を
あなたの興味にあわせてメールでお届けします。
会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。
貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!
お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?
その他の記事はこちらをCHECK
https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>
【本紙について】
・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。
・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。
【著作権について】
・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。
・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。
・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。
【免責事項】
・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。
・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。
・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。
・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。






