幼稚園や学校、職場、レジャーなど、さまざまなシーンで使用される水筒。
特に最近は、エコ意識や節約意識の高まりにより、水筒を携帯する人が増えているようです。
中でもステンレス製の水筒は、保冷も保温もできるので、便利ですよね!
そんな、日常生活で頻繁に活躍する水筒ですが、洗う手間がかかる点や、構造的に汚れが蓄積されやすい点が悩みどころでもあります。
そこで今回は、水筒の正しい洗い方を詳しく解説したいと思います。安心・安全に水筒を使うためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
毎月ポイントが貯まる
お得な「アルファあなぶきStyle会員サービス」
「アルファあなぶきStyle会員サービス」の無料会員になると、
そんな住まい情報と一緒に毎月1万ポイントをお届け。
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもさらにポイントが加算されます。
貯まったポイントは、「毎月のプレゼント応募」や「将来の住まい購入時の割引(最大50万円)」に使えます。
1.水筒を使ったあとの正しい洗い方!手順は3ステップ
水筒は、直接口をつけることが多いため、正しいお手入れをしないと汚れ・においの付着やカビの発生を招くことになります。
また、スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れる場合は、長時間入れっぱなしだとサビの原因になるので、早く洗い流すことが大切です。
日々のお手入れが正しくできているかによって、水筒の衛生状況は変わってきます。
正しい洗い方の手順は以下の3ステップ!
- ふたやパッキンは全て取り外す
- 柔らかいスポンジ+中性洗剤で洗おう
- 水分が残らないように十分に乾かす
順番に確認していきましょう。
1-1.【ステップ1】ふたやパッキンは全て取り外す

水筒を洗うときは、まず、ふたやパッキンなど、取り外せるものは全て取り外します。
特にパッキンの隙間は、お茶などの飲み物の汚れがつきやすく、そのまま放置していると、菌やカビの発生につながります。
清潔を保つためには、「ふたやパッキンを取り外す」という、このひと手間を面倒くさがらずに行ってくださいね。
1-2.【ステップ2】柔らかいスポンジ+中性洗剤で洗おう

水筒を洗うためのスポンジは、柔らかい素材のものを選びましょう。
研磨粒子が練り込まれているものなど、固い素材のスポンジは、水筒に傷がついてしまう恐れがあるので水筒洗いには適していません。
水筒についた小さな傷は、サビつきや汚れの付着につながるので注意しましょう。
洗い方としては、薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗います。
ふた、パッキン、本体をそれぞれしっかりと洗いましょう。
1-2-1.スポンジ選び ~部品毎に適したものを使い分けよう~
水筒には、ボトル、ふた、パッキンなど部品が複数あります。
部品の形状によっては、普通のスポンジでは隅々まで洗いきるのが難しい場合があります。
そのため、できれば部品に合ったスポンジも併せて準備しておくと便利ですよ。
ボトル部分
細長いボトル部分を洗うときは、柄付きのスポンジがあると便利です。普通のスポンジでは届かないボトルの底までしっかり洗えます。
本体を傷つけない柔らかい素材のスポンジを選びましょう。柄付きスポンジは100円ショップなどで簡単に手に入ります。
また、わざわざ購入しなくても、自宅にある小さめのスポンジを菜箸ではさみ、輪ゴムで固定すれば、「手作り柄付きスポンジ」になります。こちらでも十分代用ができます。
日常的に水筒を使うご家庭では「柄付きスポンジ」を一つ常備しておくことをおすすめします♪
ふたや、中栓、パッキンなど細かい部分
水筒のふたや、中栓、パッキン部分は、構造上くぼみが多いので、洗い残し汚れが気になってしまいますよね。
これらの細かい部品には、その素材やサイズにあった小型ブラシを使うと便利です。各水筒メーカーからも部品専用の小型ブラシが販売されていますし、100円ショップなどでも様々な種類が販売されています。
また、家にあるもので代用するなら、綿棒が便利です。水筒の細かい部分の汚れやぬめりを綿棒でこすると、気持ちいいほどきれいに落ちますよ♪綿棒は素材が柔らかいので、水筒の部品を傷つける心配もありません。
ストロー部分
ストロー付きの水筒の場合、ストロー部分の洗浄に悩むのではないでしょうか。直接口をつける部分ですので、水ですすいで終わりでは、衛生的に不安ですね。
ストローを洗う際は、市販されているストロー専用の細いブラシを使い、内側までしっかり洗いましょう。

ただし、ブラシ洗浄を繰り返すことで、ストロー内側には細かい傷がついてしまいます。
傷がついたことで付着した汚れが落ちにくくなってきたらストローの替え時サイン。新しいストローに替えるようにしましょう。
1-2-2.洗剤選び ~基本は「台所用の中性洗剤」でOK~
日常的な水筒洗いには、基本「台所用の中性洗剤」を使用します。あらかじめ中性洗剤をぬるま湯で薄めてから使用すると、洗剤のすすぎ残しを防ぐことができ、しっかりと洗い上げられますよ。
もし、水筒に香りがつくのが気になるなら、無香性タイプの洗剤を使うとよいでしょう。
ただし、茶しぶやカビなどの特別な汚れに対しては他の洗剤を使用することもあります。特別な手入れ方法については後ほど2章で詳しく解説しますね。
1-2-3.洗い方 ~部品を傷つけない・なくさない工夫を~
洗い方のポイントは、ゴシゴシと力を入れてこすらず、やさしく洗うこと。
スポンジを使用しても、強くこすることで細かい傷がつき、劣化の原因になるので注意しましょう。
また、中栓やパッキンなど細かい部品は、洗っているうちにうっかりなくしてしまう恐れも。そうした失敗を避けるために、小さなざるに入れて洗うのがおすすめです♪
1-3.【ステップ3】水分が残らないように十分に乾かす

洗った後は、洗剤が残らないように、しっかりすすぎます。中でも複雑な形をした部品は、特に丁寧にすすぎましょう。すすぎ残しは水筒を傷める原因になるので気をつけてくださいね。
洗剤をすすぐときは、お湯を使うと水切れがよく、乾きやすいですよ。
ボトル部分
ボトルの外側は、ぬれたままだと水滴のあとが残ったり、サビの原因にもなります。洗った後は乾いた布ですぐに拭き、内側の水分は、逆さまにして、水を切りながら自然乾燥させます。
ふたや、中栓、パッキンなど細かい部分
中栓やパッキンなど細かい部品を、他の食器と一緒に水切りかごに入れて乾かそうとすると、うっかり紛失してしまうことも。また、小さな部品なので、かごを抜け、水受け部分に落ちて水浸しになることも考えられます。
紛失防止のため、細かい部品は小さなざるに入れて洗うとよいのですが、洗った後は、その小さなざるに入れたまま、水切り・乾燥をするとよいでしょう。
もしくは、洗ったあと乾いた布やキッチンペーパーで粗方拭いて、その布やペーパーの上に置いて乾かす方法でもいいでしょう。
2.【汚れ別】日頃の手入れでとりきれない頑固な汚れの対処法
水筒を使用後にしっかり洗っていても、毎日使い続けていれば、日頃の手入れでとり切れない汚れが気になるようになります。
この章では、なかなかおちない頑固な汚れの対処法を、汚れ別にご紹介します。
2-1.茶しぶ・においには『酸素系漂白剤』

茶しぶやにおいが気になるときは、酸素系漂白剤を使って、つけ置き洗いをします。
酸素系漂白剤は汚れやにおいを取るのと同時に、除菌もできるので、毎日使う水筒は、ぜひ定期的につけ置き洗いをするよう心がけましょう。
衛生面を考えて1週間に1度の頻度で漬け置き洗いをすることをおすすめします。なお、酸素系漂白剤は、必ず説明書に沿って正しく扱ってください。
ボトル部分
- 所定量の酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)をボトルの中に入れ、約30分置きます。
誤飲を防ぐため、「つけおき中」と大きく書いた付箋をボトルにつけておくと安心です。 - 30分たったら洗浄液を捨て、柄のついたスポンジブラシでボトルを洗い、十分にすすぎます。
- 最後は、しっかり乾燥させます。
〈注意〉
ボトル部分のつけ置き中は、ふたをせず開放状態にしておくこと。
酸素系漂白剤は発泡作用があるので、ふたをつけたままだと、ふたが跳ね上がったり、破損する危険があります。また、ボトルは内側だけつけ置きをします。本体の外側に漂白液がつくと変色や傷みの原因になる可能性があるので気をつけましょう。
ふたや、中栓、パッキンなど細かい部分
- ボウルなどの容器に、所定量の酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯(40℃以下)を入れます。そこに、フタ・中栓・取り外したパッキンを約30分間つけ置きます。
- 30分たったら洗浄液を捨て、スポンジブラシなどで洗い、十分にすすぎます。
- 最後は、しっかり乾燥させます。
2-2.白っぽい水あか汚れには『クエン酸』
ボトルの内側に、白っぽいうろこ状の水あか汚れがつくことがあります。
水あか汚れは、水に含まれるカルシウムが付着したものなので、クエン酸を使ってきれいにしましょう。クエン酸は食品添加物で食品衛生上無害なので、安心して使用できます。
- ぬるま湯にクエン酸を1~2%入れ洗浄液を作ります。
(例:ぬるま湯500mlにクエン酸:約10g(小さじ2杯)) - 水筒のボトル本体に洗浄液を入れ、フタをせずに約3時間浸け置きします。
- ボトルの中のクエン酸水を捨て、十分にすすぎましょう。
- 最後は内側をしっかり乾かします。
2-3.斑点状の赤いサビには『お酢』
スポーツドリンクなど塩分を含んだ飲み物を、水筒に長時間入れっぱなしにしていると、赤サビが発生しやすくなります。赤サビは、水に含まれる鉄分が付着したものなので、お酢の力を借りてきれいにしましょう。
- ぬるま湯に酢を10%入れ洗浄液を作ります。
(例:ぬるま湯500mlに酢:50ml) - 水筒のボトル本体に、洗浄液を入れ、フタをせずに約30分間つけ置きします。
- 浸け置き後は、中の洗浄液を捨て、よくすすぎましょう。
- 最後は内側をしっかり乾かします。
2-4.水筒カバーの汚れには『洗濯用洗剤か食器用洗剤』

ボトルが傷ついたり汚れたりするのを防ぐための水筒カバーは、水滴や砂ぼこりなどで汚れやすいもの。汚れることが想定されている水筒カバーですので、そのほとんどは水洗いができます。
ただし、カバーの種類によって、洗濯機で丸洗いができるものもあれば、手洗いでしか洗えないものもあります。
まずは、洗う前に必ず水筒カバーの洗濯表示を確認し、表示に従って洗濯するようにしましょう。
洗濯表示が『手洗いのみ』の場合
- 洗剤は、洗濯用洗剤、もしくは食器用洗剤を使います。
たらいや洗面器に、水もしくは30℃以下のぬるま湯と洗剤を入れて洗浄液を作ります。 - 水筒カバーを洗浄液に約5分間つけ置きします。
- 汚れを浮き上がらせたら、手のひらを使ってやさしく押し洗いします。
- 洗い終われば、軽く絞って水ですすぎましょう。
「きれいな水を溜めて沈める」→「軽く絞る」→「水ですすぐ」の一連の流れを洗剤の泡が出なくなるまで繰り返します。 - すすぎ終われば、風通しのよいところに干して乾かします。
洗濯表示が『洗濯機使用可能』の場合
- 付属品のひもやベルトは取り外し、水筒カバーだけを洗濯ネットに入れます。
- 水もしくは30℃以下のぬるま湯と、洗濯用洗剤で洗います。
- メーカーにより表現は異なりますが「ドライコース」・「おうちクリーニング」・「手洗いコース」・「ソフトコース」など、手洗いに近い洗濯コースを選びましょう。
- 洗濯が終われば、風通しのよいところに干して乾かします
油性のシミ汚れの場合
油性のシミには直接、食器用洗剤をぬり、しばらく置いて浸透させてから、手洗い・もしくは洗濯機で洗濯すると汚れが落ちやすいです。
3.洗う時にしてはいけない3つのこと
水筒を洗う時に、してはいけないことがあります。知らず知らずのうちについやってしまいがちなNGお手入れ方法を3つ覚えておきましょう。
3-1.塩素系漂白剤は使用しない
マグカップの茶しぶ取りや、ふきんの除菌などに用いられる台所用の塩素系漂白剤ですが、水筒には洗浄力が強すぎるため使用できません。
塩素系漂白剤をステンレスの水筒に使用すると、内側部分のメッキの剥がれ、サビや保温・保冷不良を招きかねません。漂白剤を使って汚れをとりたいなら、必ず酸素系のものを使用してくださいね。
3-2. 食洗機で洗わない

食洗機があるお宅では、他の食器類と一緒に水筒も機械で洗えたら楽ですよね。
しかし、食洗機というのは、高温のお湯で食器類を洗っていきます。熱は、水筒の変形や塗装はがれ、傷、サビなど劣化の原因になるため、水筒洗いには食洗機は適していません。
手間はかかりますが、水筒は手洗いするようにしましょう。
3-3. 金たわしを使用しない
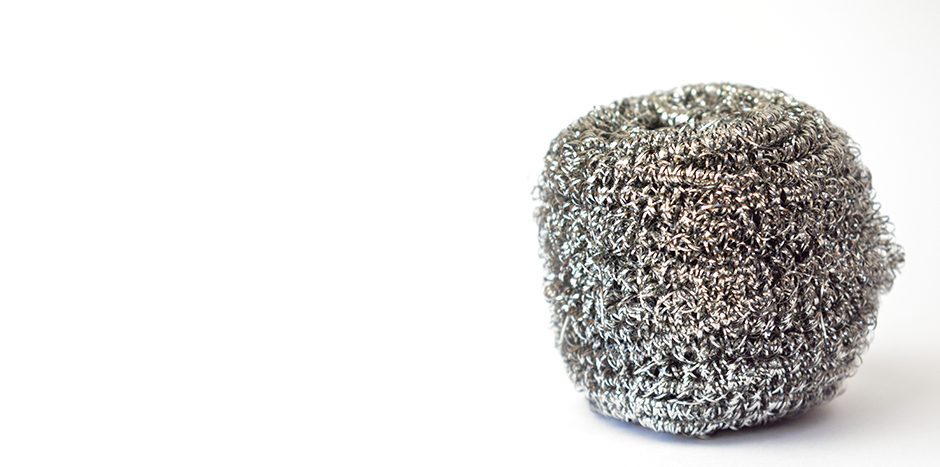
がんこな汚れを落としたくても、金たわしでこするのは厳禁です!
金たわしを使うことで、水筒には無数の傷がついてしまいます。
特に、水筒の内部が傷ついてしまうと、傷に汚れがたまっていき、雑菌が繁殖して健康被害につながることも考えられます。水筒を衛生的に保つためには、傷がつかないように気をつけなければなりません。
4.パッキンなど部品類は消耗品!定期的に点検をしよう

パッキンや中栓など取り外しができる部品は、使っていくうちに、劣化していくものです。
劣化した部品を使い続けていると、水筒の中身がもれ出す恐れがあります。そうなって困る前に、新しい部品に取り替えることをおすすめします。
水筒を洗うついでに、パッキンや中栓が傷んでいないか定期的にチェックするとよいでしょう。
黒ずみ、破れ、変形、とれないにおいなどは、劣化のサインです。
取り替えの目安は、各メーカーや製品により異なりますが、約1年ごとの交換を推奨しているケースが多いようですよ。
5.まとめ

水筒の正しい洗い方をご紹介しました。
たかが水筒のお手入れと思われるかもしれませんが、その洗い方が不十分であれば、わたしたちの健康に直接影響が及ぶので、甘く見てはいけませんよ。
正しい洗い方を実践していれば、水筒はいつも清潔な状態を保てます。毎日使う水筒だからこそ、正しい洗い方をマスターして、安心・安全に使うようにしましょうね。
暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?
「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、
- 住まいに関する最新情報
- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を
あなたの興味にあわせてメールでお届けします。
会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。
貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!
お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?
その他の記事はこちらをCHECK
https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>
【本紙について】
・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。
・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。
【著作権について】
・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。
・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。
・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。
【免責事項】
・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。
・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。
・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。
・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。






