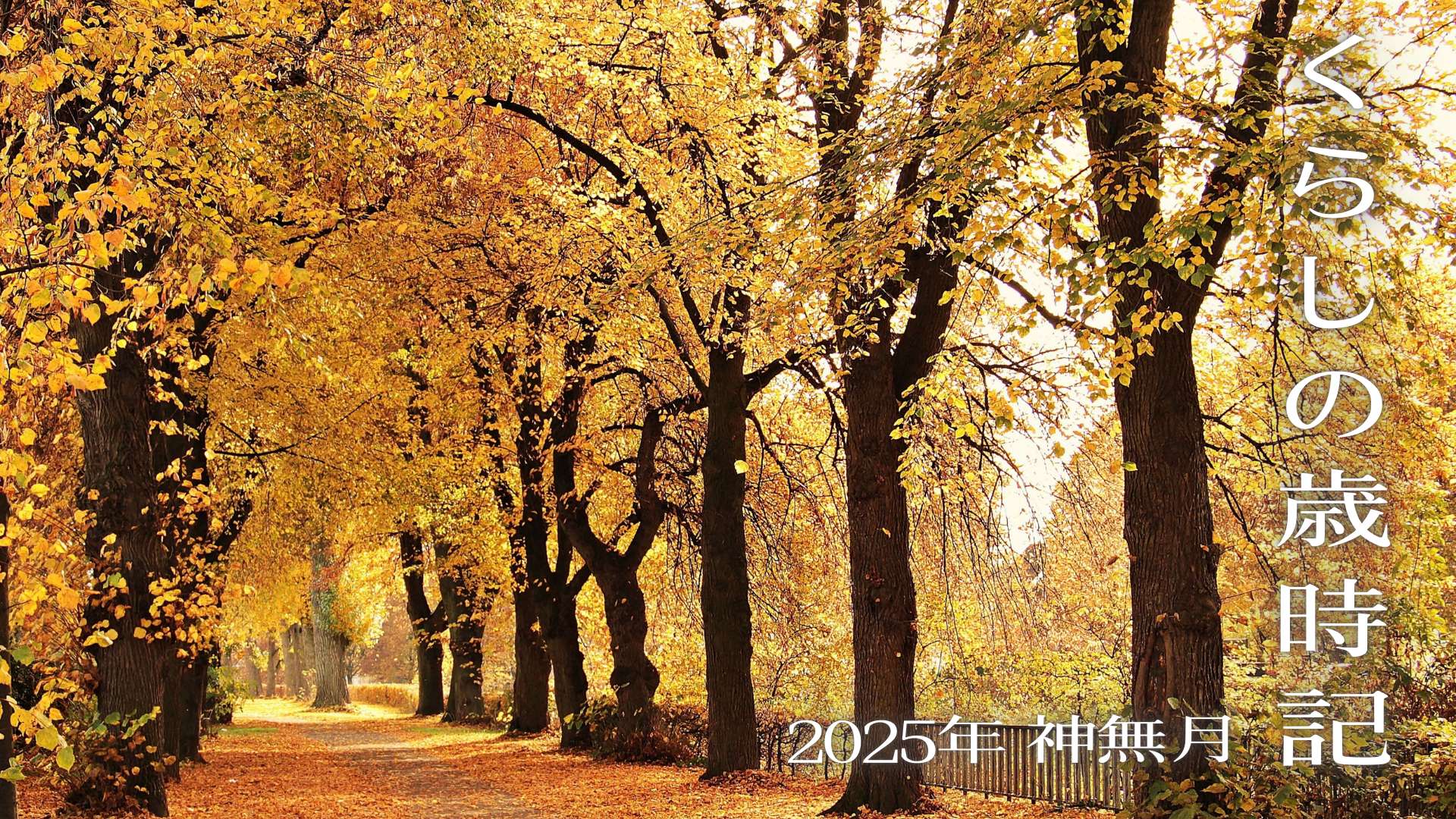10月の和名は「神無月(かんなづき)」。
この美しい響きの由来には、実は様々な説があります。
雷の鳴らない静かな月だから「雷無月」、新米で酒を醸す月だから「醸成月」など興味深い説もありますが、最も有力とされるのは、神様を祭る月だから「神の月」と呼ぶという説。
ちなみに「出雲大社に神々が集まるため諸国が神無しになる」という有名な話は、実は中世以降に生まれた俗説なのだとか。
コスモスを揺らす秋風にのって聞こえてくる、祭りのお囃子。
高く青い空を埋める白い鰯雲。色づき始めた照葉。
秋もいよいよ深まり、豊穣の季節を迎えるころ。
そんな10月のくらしの歳時記を紹介します。
10月のこよみ
10月8日「寒露」(二十四節気)
寒露とは、野の草に降りる露のこと。
日中の暑さはやんで過ごしやすくなりますが、そのぶん朝晩の冷え込みを実感するようになります。

このころになると秋の長雨シーズンも終わり、秋晴れの空気が澄んだ過ごしやすい日が多くなります。
10月20日〜11月6日「秋土用」(雑節)
雑節のひとつ「土用」は、土公神(どくじん)という土を司る神様が支配する期間のこと。季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、期間中は地鎮祭や井戸掘りなどの「土を動かす作業」を忌むことになっています。
とはいえ18日もの間ずっと作業ができないのは、さすがに実生活に影響が出ます。そこで土公神が地上を離れる日を設け、その日に限っては作業をしてもOKとしました。
それを「間日」と呼びます。
2025年の秋土用の間日は、10月21日・29日・31日、および11月2日です。
10月23日「霜降」(二十四節気)
秋がいちだんと深まり、朝霜が見られるエリアも出てくるころ。朝晩もぐっと冷え込み、日が短くなったのを実感できるのではないでしょうか。
早いところでは、この時期から冬支度を始めます。

暦の上では「晩秋」になり、秋もフィナーレを迎えます。
次の二十四節気は「立冬」。いよいよ冬の始まりです。
10月の年中行事とイベント
10月1日「衣替え」
衣替えは平安時代の宮中行事から始まった習慣。中国の風習に倣って、4月1日と10月1日に夏服と冬服を入れ替えます。

とはいえ、気候の一定しない近年では、暑い日があると思えば急に肌寒くなる日もあったりして、一概に「今日から冬装束に変わります」と言われてもピンとこないのではないでしょうか。特に近年では日中の気温がまだまだ高い日が多く、秋物を着る気分にならない人もいるかもしれませんね。
衣替えのタイミングは「最低気温が20度程度になった」あるいは「日中の気温が25度を下回るようになった」ときが最適だと言われます。風が涼しくなったと感じたら、羽織ものやストールで調整しながら、徐々に秋冬モードに移行していきましょう。
10月6日「十五夜」(中秋の名月)
「中秋」とは、文字通り秋の真ん中を指す言葉です。昔の暦では7月から9月までを秋としていたため、その中心にあたる8月15日(旧暦)に月を愛でる習慣が生まれました。
このお月見の風習は、平安時代に中国(唐)から日本に伝えられたとされています。はじめは宮中や貴族たちの雅な行事でしたが、やがて武士や商人、そして庶民へと広がっていきました。
時代を超えて愛され続けてきたお月見。今もなお多くの人に親しまれているのは、月の美しさが人の心を魅了してやまないからなのでしょう。

十五夜のお供え物
お月見といえば、風にそよぐススキと、まあるい月見だんご。
この慣わしは、月の満ち欠けを頼りに農作業を営んできた昔の人々が、豊かな収穫への感謝を込めて月にお供え物をしたことに始まります。
月見だんごと共に供えられるのは、その時々の旬の恵み。
十五夜の頃ともなれば里芋の新物が出回る季節です。そのため十五夜は「芋名月」という美しい別名でも親しまれてきました。
中秋の名月は「満月」とは限らない
「十五夜・中秋の名月といえば満月」。
そんなイメージをお持ちではないでしょうか?
実は、十五夜が必ずしも満月とは限らないのです。
昔の暦である旧暦では、毎月1日を「朔(さく)」と呼び、新月の日(月齢0)と定めていました。そして1ヶ月の日数も、月の満ち欠けの周期に合わせて決めていたのです。
そのため旧暦の十五夜は、確実に満月の夜でした。
ところが現在私たちが使っている新暦は、太陽の動きを基準にして作られています。
新月から満月までの日数は13.9日から15.6日と幅があるため、15日目である十五夜が必ず満月になるとは限らないのです。
それでも秋の夜空に浮かぶ月を眺めながら、古の人々が同じように月に想いを寄せていたことを思うと、心が静かに満たされるような気がしませんか。
ちなみに今年は十五夜の翌日、7日が満月となっています。
月はありのままを愛でる
お月見の夜には、澄み渡った夜空に浮かぶ美しい月を眺めたいと願うものです。
けれど昔の人たちは、雲に隠れて月が見えない夜を「無月(むげつ)」、雨に煙る夜を「雨月(うげつ)」と名付けました。月の姿が見えずとも、それぞれに趣深いものとして愛でていたのです。
雲間に隠れた月に思いを馳せ、雨音に耳を澄ませながら月の存在を感じる。そんな奥ゆかしい感性に、日本人の美意識の豊かさを見ることができるのではないでしょうか。
見えないものにこそ宿る美しさ——それもまた、お月見の醍醐味なのかもしれません。
10月31日「ハロウィーン」
ハロウィンは古代ケルトの収穫祭がルーツといわれるお祭りです。
秋の収穫を祝い、悪霊を追い払う行事でしたが、現在はジャック・オ・ランタンを飾ったり、魔女やオバケなどに仮装するイベントとして定着していますね。

楽しいイベントの反面、毎年のことなので、そろそろネタが尽きてしまった…という声を聞きます。
ハロウィーン風の飾りをあしらったり、ハロウィーンモチーフのお菓子を作ったり。親子で簡単に楽しめるアイデアを集めました。

しっとり大人に楽しみたい方向けには、ハロウィーンがモチーフの浮島(和菓子)レシピがオススメ。

ハロウィンが終われば、秋も終わり。
いよいよ冬の到来です。
10月の自然を表す「ことば」

いわし雲│いわしぐも

秋の空を見上げると、小さな雲がまるで魚の群れのように連なって浮かんでいることがあります。これが「いわし雲」です。
正式には巻積雲(けんせきうん)と呼ばれるこの雲は、地上から5000~1万5000メートルもの高い空に現れます。無数の小さな雲片が規則正しく並ぶ様子が、銀色に光るいわしの群れを思わせることから、この美しい名前で親しまれています。「うろこ雲」という呼び方もありますね。
澄み切った秋の青空に白く輝くいわし雲は、見る者の心を軽やかにしてくれます。しかし、この雲が空に広がるのは低気圧や前線が近づいているサイン。美しい姿とは裏腹に、数日後には天気が崩れることを告げる雲でもあるのです。
束の間の美しさだからこそ、いっそう心に残るのかもしれません。
釣瓶落とし│つるべおとし

「秋の日は釣瓶落とし」
昔の人が残したこの美しい諺は、秋の太陽がまるで一瞬にして地平線に沈んでしまう様子を表現した言葉です。
「釣瓶(つるべ)」とは、井戸の水を汲むときに使う桶のこと。
長い縄を付けたこの桶を滑車にかけて井戸の底に落とすとき、重みに引かれてスルスルと一気に降りていく様子があります。昔の人は、その釣瓶が落ちる速さと秋の夕日が西の空に沈む早さを重ね合わせ、印象的な比喩として表現したのです。

夏の長い一日に慣れた心に、ふいに訪れる短い秋の日。気がつけばもう夕暮れという、あの少し寂しいような感覚を、井戸端の日常風景に託した先人の感性には、思わず感嘆してしまいます。
照葉│てりは

秋の陽だまりを歩いていると、紅葉した葉が光を受けて宝石のように輝いている光景に出会うことがあります。この美しい情景を表すのが「照葉(てりは)」という言葉です。
照葉とは、紅や黄に色づいた葉が秋の陽光を受けて美しく光り輝いている様子、またはその輝く紅葉そのものを指します。
秋は空気が澄み切り、湿度も低くなるため、夏よりも太陽の光がくっきりと感じられる季節です。そんな透明感のある秋の日差しが紅葉を照らすとき、葉の一枚一枚がまるで内側から発光しているかのように美しく輝きます。
古の歌人たちも愛でた「照葉」の美しさ。足を止めてその輝きに見入る瞬間は、忙しい日常に小さな幸せをもたらしてくれるものです。
山粧う│やまよそおう

秋が深まる頃、山々を眺めると木々が赤や黄、橙色に染まり、まるで山全体が美しい装いをしているように見えることがあります。この晩秋の情景を表現するのが「山粧う」という雅な言葉です。
夏の緑一色だった山肌が、いつしか錦絵のような彩りに包まれる様子。それはまさに山が季節の装いを身にまとい、最も美しい姿で私たちの前に現れる瞬間といえるでしょう。
「粧う」という言葉には、ただ色づくだけではなく、心を込めて身を飾るという意味が込められています。自然が織りなす壮大な美の演出を、まるで女性が鏡の前で装いを整えるような優雅さで表現した、日本語の美しさを感じさせる言葉です。
遠くの山並みを見つめながら、「今年も山が粧ったな」とつぶやいてみる。そんな秋の一日も、また格別なものです。
今月のアンケート
みんなの暮らし聞いてみました! \こんなとき、どうしてる?/
わざわざ聞かない。聞けないけど、ずっと気になっている日常生活のアレコレ…「そういえば、みんなどうしてる?」をリサーチしてお届けします!
今月のお題は「音楽の愉しみ方」

定額制の配信サービスやSNSの普及により、以前とは音楽を楽しむスタイルが変わってきました。
また各地で様々な音楽イベントが開催されることも増え、生で音楽を聴く機会も増えています。
今回は、皆さんの音楽の愉しみ方についてお伺いします。
回答期限:2025年10月16日(木)
アルファあなぶきStyleのサイトに移動します
先月の「冷蔵庫」の集計結果をみる

毎日の生活を支える冷蔵庫。最近では扉の形状や省エネ性能、スマホとの連携などの機能が増え、選ぶポイントも多様化しています。
今回はみなさんの冷蔵庫の使い方や購入基準についてお聞きしました。
アルファあなぶきStyleのサイトに移動します
次回の「くらしの歳時記」は11月・霜月編。お楽しみに!
暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?
「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、
- 住まいに関する最新情報
- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を
あなたの興味にあわせてメールでお届けします。
会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、
アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。
貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!
お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?
その他の記事はこちらをCHECK
https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>
【本紙について】
・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。
・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。
【著作権について】
・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。
・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。
・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。
【免責事項】
・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。
・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。
・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。
・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。