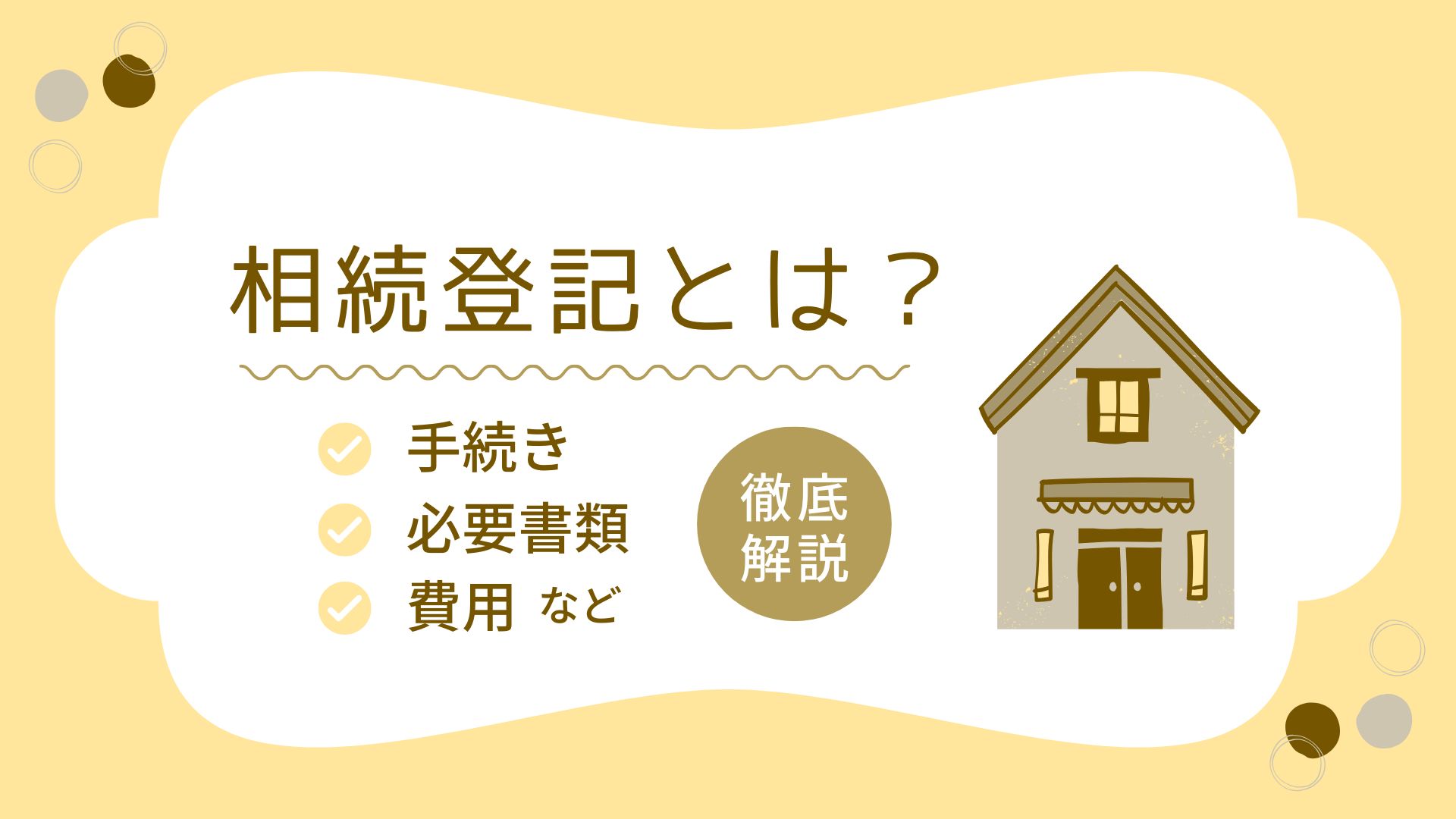2024年4月1日から不動産登記法が改正され、相続登記の義務化が始まりました。不動産の登記名義人が亡くなったら、相続登記をしなければならないという新ルールです。亡くなった方の名義のままとなっている不動産を抱えている相続人の方にとっては、相続登記の義務化の内容、今後の手続き方法について心配されているのではないでしょうか。
しかし「登記」とは、普段の生活でなじみのないものです。いつまでにやらなければいけないのか、どのくらいの費用がかかるのか、わからないことばかりでしょう。
そこで本記事では、相続登記の基本から、新たに始まったルールまでわかりやすく詳しく解説します。すでに相続問題に直面している方はもちろん、今後、相続を控えている方も、新たに義務化された相続登記の内容について知っておきましょう。
会員限定でポイントが貯まる
「アルファあなぶきStyle会員サービス」
アルファあなぶきStyle会員サービスは、会員限定で条件に合うマンション情報や、暮らしに役立つ記事をお届けします。
さらに、登録するだけで1万ポイント(1pt=1円)がすぐにもらえ、以後も毎月自動で1万ポイントを付与。
貯めたポイントはマンション購入時に最大50万円の割引として使えます。
「まだ検討中…」という段階でも、お得を先に積み立てておけるサービスです。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の登記名義人(登記簿上の所有者)が死亡した場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続きです。名義変更の手続きは、法務局に登記申請することによって行います。
そもそも不動産登記制度は、権利関係を公示することで「第三者に対抗する」「不動産取引や担保設定の安全性を高める」等のためにあります。相続人も法定相続分以上の取得分については、登記を備えなければ第三者に対抗できません。
これまで相続による不動産登記名義の変更は任意でしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。その背景には、所有者不明土地問題があります。費用がかかるなどの理由で長期間相続登記がされず、所有者がわからなくなってしまった不動産が増え、社会問題となっているのです。相続登記の義務化には、所有者不明土地の発生を予防し、土地の利活用を円滑にしたいという狙いがあります。
相続登記は自分で出来る?
相続登記が義務化されたことを踏まえ、登記申請を自分できないかと考える方もいるでしょう。結論として、時間とゆとりがあれば、自分で行うことはできます。ただし、相続関係が複雑化していたり、物件が多岐にわたっていたりする場合は、書類作成や添付書類の収集に時間や労力がかかることが想定されるため、自分で登記申請をすることは困難かもしれません。
司法書士に依頼することで、登記手続き以外にも相続全般の手続きをスムーズに進めることができます。また、戸籍の取得や法定相続情報一覧図の作成など、相続登記に直結する業務はもちろん、預貯金の解約手続きの代行など相続登記以外の遺産整理事務支援も行うことが可能です。
もし、自分で相続登記するのが大変そうだと思ったら、専門家である司法書士に相談しましょう。費用はかかりますが、煩雑な相続登記に対する悩みから解放されるので、精神的にも楽になります。
相続登記を行う期限
今回の法改正で、相続登記を行う期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」と定められました。相続人は、特別な事情がなければ被相続人が亡くなって相続が開始したことをすぐに知り得る立場にありますので、「知った日」は被相続人が亡くなった日ということが多いでしょう。
ただし、被相続人が不動産を所有していたかどうかわからないということもあります。この場合、被相続人が不動産を所有していたことが判明するまで、相続登記の義務はありません。また、相続人の1人が相続放棄をした場合、他の相続人は、当該相続放棄を知った日から3年以内に相続登記を行う義務を負います。
相続登記を行うためは、相続人の間で誰がどのように相続財産を分けるかを決めなくてはいけません。本来であれば早めに遺産分割の話合いを行い、誰が不動産を相続するかを決めて、期限内に相続登記することが求められます。しかし、誰が不動産を相続するのかがすぐに決まらないため、相続登記ができないという場合もあるでしょう。例えば、相続人間でトラブルが発生し、話合いでの解決に時間がかかりそうな場合です。
このように、事情があって申請期限を過ぎても相続登記が完了しそうにない場合、期間内に法務局へ相続人であることを申し出れば、相続登記の義務を果たしたと認められる制度が出来ました。これが、相続人申告登記です。
相続人申告登記とは、相続登記の義務を履行するために設けられた簡易な手続きです。自分が相続人であることを法務局に申告するだけで相続登記の義務を果たすことができ、他の相続人の同意がなくても相続人1人1人が手続きできます。なお、手続き費用は無料です。添付書類は申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本だけなので、相続人の負担の軽減が図られています。
しかし、ここで注意が必要です。相続人申告登記はあくまで相続登記の義務を果たすための登記であり、相続登記ではありません。そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合は、本来の相続登記を行う必要があります。つまり、自己のために相続があったと知った日から3年以内に、法定相続分、遺言書、または遺産分割協議書に基づく相続登記を行う、もしくは相続人申告登記を行う必要があります。
3年以内に遺産分割協議ができない場合
3年以内に相続人申告登記もしくは法定相続分での相続登記を行うことで相続登記の義務を果たしたことになりますが、遺産分割協議が成立したら、協議成立の日から3年以内に遺産分割協議に基づく相続登記を行なう必要があります。
相続登記の具体的な手続きの流れについては、後ほど詳しく解説します。
相続登記しない場合のデメリット
相続登記が義務化されているにもかかわらず、相続登記をしなかった場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。以下に、代表的なデメリットをまとめました。
申請義務違反として過料の適用対象となる
相続不動産があるのにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときには、10万円以下の過料の適用対象となります。正当な理由とは、相続人が極めて多数で戸籍関係書類等の収集や相続関係の把握に時間を要する場合や、遺産について相続人同士で争いになっている場合などとされています。
相続した不動産を売却できない
亡くなった方の名義になっている不動産は、そのままの状態では売却することができません。相続登記をして、相続人の名義にしてから売却する必要があります。不動産の売買に伴って行う所有権移転登記は、不動産の登記名義人である売主と買主の共同申請になるためです。
また、すでに完済した住宅ローンなどの抵当権が登記されたままになっていて、その抵当権を抹消しようとする場合にも、前提として相続登記が必要です。
担保設定ができない
銀行で融資を受ける際、不動産に担保設定をすることが条件となることがあります。この場合、担保設定をする不動産の登記名義人が亡くなった方のままだと、担保設定の登記ができないため、融資を受けられなくなる可能性があります。
以上のように、相続登記を怠っているとさまざまなデメリットがあります。相続が発生し、相続財産の中に不動産がある場合には、速やかに相続登記を行うようにしましょう。
過去に相続したものの未登記の物件についてはどうなるのか
相続登記の申請義務化の施行日である令和6年4月1日より前に開始した相続についても、義務化の対象となります。施行日前に開始した相続に関する相続登記の申請期限は、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年3月31日です。
相続登記の流れ
実際に相続登記をする場合の手順を、以下にまとめました。相続登記をせずに時間が経ってしまうと、相続関係が複雑化してしまう可能性があります。書類の準備や相続人間の話し合いなどは、思った以上に時間がかかることが少なくありません。そのため、早めに準備しましょう。
1.司法書士に相談する
相続登記が必要になったら、まずは司法書士に相談してみましょう。全国の司法書士会では、無料の電話相談や面談での相談を行っています。また、法務局でも予約制の無料相談を行っていますので、利用してみると良いでしょう。
無料相談では、登記申請書の具体的な作成指導などは行いませんが、相続登記に関する一般的な内容について相談できます。まずは一度相談してみて、自分で登記申請できるのか、専門家に頼む方がよいかを検討してみるという使い方がおすすめです。また、ご自宅を購入したときに登記を依頼した司法書士に相談するのも一つの方法です。
なお、司法書士に相続登記を依頼することで、必要な戸籍関係書類を職権で取得してもらうことができます。遺産分割協議書を作成してもらうことも可能なため、相続登記にかかる手間が大きく省けるでしょう。
2.相続する不動産の確認
相続登記をする上で、実際に相続する不動産の確認は必須です。被相続人宛てに届いていた固定資産税の納税通知書や、自宅に保管してあった権利証などで、不動産の内容を確認しましょう。所有している不動産が多い場合は、役所の税務課で評価証明書や名寄帳を取得することで、管轄内に所有している不動産をまとめて把握することができます。
ただし、道路持分など課税されていない部分については、記載されていないこともあるので注意が必要です。不動産全部が把握できないと、登記漏れが発生する原因となります。相続登記が終わった後に登記漏れが発覚し、再度相続登記を行うことになると負担が大きいので、漏れがないように不動産の内容を確認しましょう。なお、他府県の不動産がないか、山林などの共有不動産がないかもチェックすべきポイントです。
今後、相続財産となる不動産がどれくらいあるかわからない場合は、所有不動産記録証明書で把握できるようになります。この新制度は、令和8年2月2日に施行されることが決まっています。
3.不動産を取得する相続人を決める
相続財産である不動産を把握できたら、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。1人の相続人が相続することも、複数人の共有とすることも可能です。
不動産を取得する相続人を決める方法として、主に以下3つのパターンがあります。
①法定相続分どおりに取得する
②遺産分割協議で決定する
③遺言書の内容に従う
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
①法定相続分どおりに取得する
例えばお亡くなりになった方の相続人が配偶者と2人の子だとしましょう。この場合、民法で定められた相続分は配偶者が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
民法で定められた相続分通りに被相続人の相続財産を分けることを、法定相続と言います。不動産を法定相続分で相続登記した場合、前述の例では配偶者と2人の子、計3名の共有名義となります。
②遺産分割協議で決定する
遺産分割協議は、相続人の中で話合いを行い、法定相続分とは別の分け方を決める方法です。相続人の1人が単独で相続すると決めることも、複数の相続人が共同で相続すると決めることも可能です。また、1人の相続人が不動産全部を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払うと決めることもできます。これを代償分割と言います。
遺産分割協議は、必ず相続人全員の合意が必要です。しかし、相続放棄をした相続人については初めから相続人ではなかったとみなされるので、遺産分割協議へ参加する必要はありません。
③遺言書の内容に従う
被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書の内容どおりに相続財産を分けます。遺言書が被相続人の自宅から発見された自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。検認とは、相続人の面前で裁判官が遺言書を開封し、中身を確認するという手続きです。相続登記を申請する際には、検認が完了した後の遺言書が添付書類となります。なお、公正証書遺言及び法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。
遺言書があれば、その内容が優先され、遺言書が無い場合は話合いで遺産分割協議を行うことが一般的です。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人の1人が認知症を患っていれば成年後見制度を利用したり、相続人の1人が未成年者なら特別代理人の選任を行ったりしなければなりません。
戸籍調査の結果、新たな相続人が判明することがあるかもしれません。この場合は、その相続人を含めて話合いが必要です。なお、話合いで協議がまとまらなければ、裁判所の調停を利用することになります。
相続登記後に不動産の売却をする場合は、相続人1人の単独所有として相続登記をした方がスムーズです。共有名義にしてしまうと、共有者全員のスケジュールを合わせたり、それぞれ書類を用意したりという手間がかかってしまいます。また、売却方針で意見が分かれる可能性もあるでしょう。ただし、相続税との兼ね合いもあるので、慎重に検討してください。
4.相続登記に必要な書類を用意する
相続登記をする際に必要な書類は、次の通りです。
<亡くなった方(被相続人)に関する書類>
| 書類名 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは除籍謄本 | 法定相続による登記、遺産分割協議による登記で必要。遺言書がある場合には、被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本もしくは除籍謄本のみで良い。 また、代わりに後述の法定相続情報一覧図を添付することも可能。 | 広域交付制度により最寄りの市区町村役場で取得することが可能だが、一部の戸籍のみ本籍地の役場で取得が可能。 |
| 住民票の除票もしくは戸籍の附票の写し | 登記上の住所と本籍が一致する場合は不要。 本籍地が記載されている必要がある。住民票もしくは戸籍の附票の住所が、登記簿上の住所と異なる場合には、登記簿上の住所まで繋がるものが必要。 | 住民票は被相続人の住所地の市区町村役場で取得する。戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得する。戸籍の附票は広域交付制度の対象外となっている点に注意が必要。 |
<相続人に関する書類>
書類名 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 代わりに後述の法定相続情報一覧図を添付することも可能。 | 広域交付制度により最寄りの市区町村役場で取得することが可能。 |
不動産を取得する相続人の住民票もしくは戸籍の附票の写し | 本籍地の記載があるものが必要。 相続人の住所が書いてある法定相続情報を添付する場合には不要。 | 住民票は相続人の住所地の市区町村役場で取得する。戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得する。戸籍の附票は広域交付制度の対象外となっている点に注意が必要。 |
<相続の内容に関する書類>
ケース | 必要書類 |
|---|---|
公正証書遺言がある場合 | 遺言書原本が必要 |
自宅で見つかった自筆の遺言書がある場合 | 裁判所で検認を受けた後の遺言書原本が必要 |
法務局で保管している自筆証書遺言がある場合 | 遺言書情報証明書が必要 |
遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる配分を行う場合 | 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要 相続放棄をした相続人がいる場合には、当該相続人の相続放棄申述受理証明書が必要 |
<登記申請に関する書類>
書類名 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
登記申請書 | 司法書士に依頼する場合には、司法書士が作成する。 | 法務局のホームページでダウンロードが可能な他、法務局でも取得可能。 |
委任状 | 司法書士に依頼する場合に必要。 |
|
評価額がわかる書類 | 評価証明書や固定資産税納税通知書など、不動産の評価額がわかる書類が必要。 | 評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場で取得可能。固定資産税の納税通知書は毎年4月頃所有者宛てに送付される。 |
<被相続人に子どもがなく、両親も亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になる場合>
書類名 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
先順位の相続人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは除籍謄本 | 法定相続による登記、遺産分割協議による登記で必要。遺言書がある場合には、被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本もしくは除籍謄本のみで良い。 また、代わりに後述の法定相続情報一覧図を添付することも可能。 | 広域交付制度により最寄りの市区町村役場で取得することが可能だが、一部の戸籍のみ本籍地の役場で取得が可能。 |
<代襲相続が発生している場合>
書類名 | 概要 | 取得方法 |
|---|---|---|
被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは除籍謄本 | 法定相続による登記、遺産分割協議による登記で必要。遺言書がある場合には、被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本もしくは除籍謄本のみで良い。 また、代わりに後述の法定相続情報一覧図を添付することも可能。 | 広域交付制度により最寄りの市区町村役場で取得することが可能だが、一部の戸籍のみ本籍地の役場で取得が可能。 |
上記表で出てきた「法定相続情報一覧図」は法務局が発行してくれる書類で、現在の相続人を証明してくれるものです。法務局に申出書と戸籍謄本等の添付書類を添付して提出すると無料で交付を受けることができ、取得することで以下のようなメリットがあります。
- 法定相続情報一覧図を添付することで、登記申請時に戸籍謄本の原本を提出する必要が無くなるので同時に他の手続きを進めることができる。さらに、法定相続情報一覧図に記載されている法定相続情報番号を申請書に記載すれば、法定相続情報一覧図の添付も省略が可能。
- 預貯金口座の相続手続きの際、金融機関によっては、戸籍謄本を提出して手続きしてもらうよりも法定相続情報一覧図を提出して手続きをしてもらった方が、手続きにかかる時間が短くなる。
法定相続情報一覧図は、相続登記の登記申請や金融機関での相続手続きの他、年金手続きや相続税の申告にも使うことができます。そのため、相続登記以外にも相続に関する手続きが必要な方は、交付を受けるのがおすすめです。
5.申請書を作成する
必要な書類が揃っても、それを法務局に提出すれば相続登記ができるというわけではありません。相続登記を申請するための申請書の作成が必要です。相続登記の申請書は法務局のホームページからひな形を入手でき、以下のひな型がそれぞれ用意されています。
- 法定相続用
- 遺産分割協議用
- 公正証書遺言用
- 自筆証書遺言用
- 数次相続用
- 相続人に対する遺贈登記用
また、法務局にも申請用紙が置いてあります。
相続登記はパターン別で申請書に記載する内容が異なっており、登録免許税の計算方法など細かいルールがあるため、一般の方はわかりづらいかもしれません。もし、必要書類を全て集め終わり、あとは申請書を作成するだけという状態でも、申請書の書き方がわからなければ司法書士に相談しましょう。
6.法務局へ申請
登記に必要な書類が揃い、申請書の準備も整ったら、不動産を管轄する法務局へ登記申請します。登記申請の方法は以下の3つです。
- 窓口に持参して申請する
- 郵送で申請する
- インターネットを利用したオンライン申請
相続登記の申請書と登記用の委任状以外の書類は、原本の返却が可能です。そのため、戸籍謄本等の添付書類の原本が必要な場合は、原本還付の手続きを取ります。
具体的には、原本を返却してほしい書類のコピーを取り、コピーに「原本に相違ない」旨を記載しますが、大量の戸籍謄本のコピーを取るのは大変でしょう。そこで、被相続人と相続人の戸籍謄本については、相続関係を示す相続関係説明図を作成して添付することで、コピーを取らなくても原本還付してもらうことが可能となっています。
7.登記識別情報通知を受取る
登記を申請してから登記が完了するまでは、管轄にもよりますが、1週間~3週間程度かかることが多いでしょう。管轄によっては、1か月以上かかる場合もあります。
登記が完了すると、登記完了証と不動産の登記名義人ごとに登記識別情報通知が発行されます。法務局から登記完了証と登記識別情報通知、そして還付してもらう書類を受取ったら相続登記が完了です。司法書士に依頼する場合は、書類の受取りまですべて司法書士が行いますので、依頼者は司法書士から書類を受け取って相続登記が完了となります。
登記識別情報通知とは、昔でいう権利証と呼ばれる書類と同じものです。普段使う機会はありませんが、不動産の売却や金融機関で不動産を担保に融資を受ける場合に必要となります。そのため、紛失や盗難に遭わないよう大事に保管してください。
相続登記に必要な費用
相続登記で必要になるのは、登録免許税と司法書士報酬、戸籍謄本代や郵便代などの各種実費です。登録免許税と各種実費は必ずかかる費用ですが、司法書士報酬については、自分で相続登記の申請をする場合はかかりません。
登録免許税
相続登記に必ず支払わなければいけない登録免許税ですが、税率は以下の通りです。
・課税価格×1,000分の4
課税価格は、登記申請をする年の固定資産税評価額です。毎年4月頃に所有者宛てに送付される固定資産税納税通知書の課税明細に、評価額が記載されています。例えば評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円です。
固定資産税評価額は3年に一度「評価替え」によって価額が見直されていますが、地価が上昇すると評価額も上がりますので、登録免許税にも影響があります。つまり、評価額が上がると必然的に登録免許税も高くなるため、今後、評価額が上がりそうな土地建物は早めに登記した方が良いということです。
なお、登録免許税の免税措置もあり、以下2つの場合には登録免許税がかかりません。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合に、その死亡した方の名義にするための相続登記。
- 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記。
この免税措置を受けられる期限は、令和7年3月31日までとなっています。
登録免許税の納付方法は、主に収入印紙で納付する方法と電子納付の2つです。電子納付は、オンラインで申請するときに限り可能な方法となります。
収入印紙は全国の郵便局のほか、法務局内で購入することが可能です。収入印紙で納付する場合、まずは収入印紙を購入し、購入した収入印紙を貼付用紙に貼り付け、申請書と合わせて提出します。登録免許税は登記申請時に納付することになるため、後払いや分割払いで支払うことはできません。
司法書士の報酬
依頼内容や依頼する司法書士によっても、司法書士の報酬が異なります。参考として、相続人が配偶者と子供2人、不動産が被相続人の単有名義の土地と建物だけであれば、報酬は5万円~10万円程度が目安となるでしょう。報酬に登録免許税額と実費を加算した額が、司法書士に支払う登記費用ということになります。例えば不動産の数が多い、管轄の異なる不動産がある、数次相続(※)が発生しているなどの事情があれば、報酬がより高額になる可能性があります。
事前に登記費用の見積もりを取ることは可能ですが、最終的な登記費用は依頼を受けてから確定することが多いでしょう。ホームページで報酬表を掲載している司法書士事務所もありますので、参考にすると良いかもしれません。
ただし、司法書士は相続人間のトラブルに関与できません。相続人同士でトラブルが生じれば弁護士への相談が必要になるため、場合によって弁護士費用もかかることを覚えておいてください。
(※)数次相続とは、被相続人の遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が開始している状態のこと。
各種実費
登録免許税と司法書士への報酬の他にかかるのが、戸籍謄本などの取得費用です。役所で取得する必要書類のうち、主な書類の手数料は次の通りです。
書類名 | 手数料 |
|---|---|
除籍謄本 | 750円 |
戸籍謄本 | 450円 |
住民票の写し | 約200円~300円(自治体により異なる) |
戸籍の附票の写し | 約200円~300円(自治体により異なる) |
印鑑証明書 | 300円 |
郵送で戸籍謄本などの書類を取得する場合には、往復の郵送代が必要になります。また、相続登記の申請を郵送で行う際には書留で送る必要があるため、書留代が必要です。なお、登記完了後の書類を郵送で受け取る場合は本人限定受取郵便と定められており、その分の郵便切手を貼った返信用封筒の同封が求められます。
さらに、相続登記が完了したことを確認するための、登記事項証明書の取得費用がかかります。こちらは、法務局の窓口で申請して交付を受けると1通600円です。土地と建物それぞれ1つずつある場合は、2通取得することになるため1,200円かかります。
なお、法務局の窓口で申請する場合には、法務局までの交通費もかかるでしょう。自分で相続登記を申請したものの、記入漏れや記載ミスが見つかり補正の連絡があれば、加筆訂正のために再度法務局へ行かなくてはいけません。
その他の税金について
相続登記にかかる税金は、基本的に登録免許税のみです。相続登記の場合、不動産取得税はかかりません。また、固定資産税については、新たに不動産を取得する相続人が納税者となります。そして、相続税は相続財産の額によって申告が必要かどうか決まるため、相続登記の有無は関係ありません。
相続登記完了後、相続した不動産を売却する場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を使って、納付額を抑えることができることもあります。そのため、相続不動産の売却を検討している方は、事前に税理士などの専門家に相談しましょう。
まとめ:動画で解説
相続登記は、被相続人の登記名義となっている不動産の名義を相続人名義に変更する登記のことで、令和6年4月1日から義務化されました。今後は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。令和6年4月1日以前に開始した相続についても義務化が適用され、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
相続登記は自分でもできますが、相続人が多かったり相続関係が複雑だったり、あるいは不動産が多かったりする場合などは、自分で登記申請をするのが困難な可能性があるでしょう。そのため、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
相続登記を行わず、不動産の名義を被相続人の名義のままにしていると、相続登記の申請義務違反になってしまいます。また、不動産の売却ができない、担保設定ができないなどのデメリットがあるので、相続する内容が決まったら早めに相続登記しましょう。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
気になる住まい探し、一歩進めませんか?
「アルファあなぶきStyle会員サービス」に登録すると、
- 登録時に1万ポイント
- その後も毎月1万ポイント を進呈します。(1pt=1円)
貯まったポイントはマンション購入時に最大50万円の割引としてご利用いただけます。
会員限定で条件に合ったマンション情報や、
暮らしに役立つコラムもお届けしています。
「まだ検討中…」という段階でも、
今のうちに始めて、将来の選択肢を広げませんか?
その他の記事はこちらをCHECK
https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>
【本紙について】
・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。
・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。
【著作権について】
・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。
・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。
・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。
【免責事項】
・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。
・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。
・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。
・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。